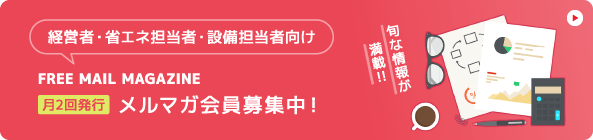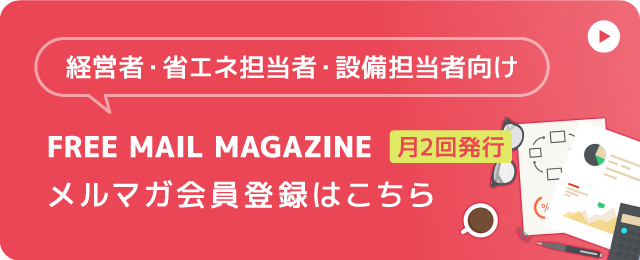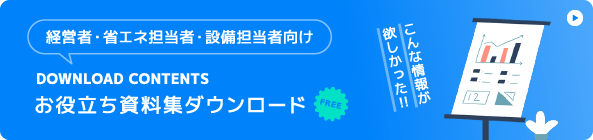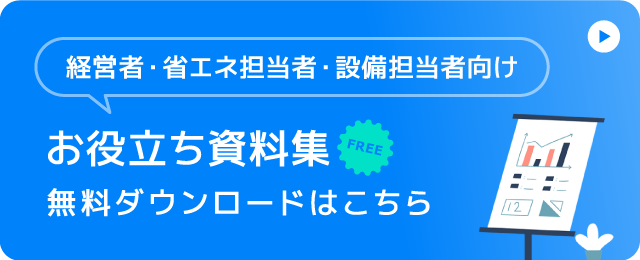コラム
コンテンツ
2012年に始まった固定価格買取制度(FIT)を追い風に、日本の再生可能エネルギーの主役となった太陽光発電ですが、今、その普及拡大の裏で起こっているのが、「パネル廃棄問題」です。
太陽光発電が普及始めた当時、環境に優しい設備として設置されたパネルが、20~30年の寿命を迎え、2030年代後半から大量にその役目を終え始めます。
その量は、国の推計によれば2030年代後半にピークを迎え、年間50万トンから最大で約80万トンに達すると予測されています。
[出典: 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」]
これは国内の産業廃棄物最終処分場の残余年数を大きく揺るがしかねないほどのインパクトです。
「まだ先の話」と思われるかもしれませんが、適切な準備なくしてこの問題を乗り越えることはできません。
廃棄のための法的なルールは?
費用は一体いくらかかるのか?
そして、誰に頼めばいいのか?
今回は、太陽光発電設備の所有者様はもちろん、これから設置を検討している方、環境問題に関心のある方に向けて、国の公表情報や法律に基づき、太陽光パネルの廃棄に関する疑問に答えていきます。基礎知識から具体的な手続き、費用、信頼できる業者の選び方まで解説します。
1.なぜ今、太陽光パネルの廃棄が問題視されるのか?
【普及の背景にある「FIT制度」】
2012年に国は再生可能エネルギーの普及を加速させるため「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(現:再エネ特措法)」に基づき「固定価格買取制度(FIT制度)」を開始しました。
これは、太陽光・風力・水力・バイオマスなどで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを義務付ける制度です。
この制度は事業者の参入を強力に後押しし、日本中の屋根や遊休地に太陽光パネルが設置されるブームを巻き起こし、日本の太陽光発電導入量は世界でもトップクラスにまで成長しました。
【処理体制が追いついていない現実】
問題は、今後排出される膨大な量の廃棄物を適切に処理するための社会的なインフラや法整備が、まだ十分に整っていない点にあります。
●リサイクルの課題
太陽光パネルにはガラスやアルミ等の有価物のほか、鉛、セレン、カドミウムといった有害物質を含むものがあります。これらを適切に分離しリサイクルするには、高度な技術とコストが必要となります。
[出典: 環境省「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」]
●不法投棄のリスク
適切な処理ルートが確立されず、費用負担を免れようとする事業者による不法投棄が懸念されています。
2.【重要】太陽光パネル廃棄の基本ルールと法律
「廃棄」と一言で言っても、そこには守るべき法律とルールが存在します。国の法律や制度に基づき、重要なポイントを解説します。
【原則は「産業廃棄物」。排出事業者責任が問われる】
大原則として、太陽光パネルは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」に基づき、「産業廃棄物」に分類されます。
具体的には、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類の混合物に該当します。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項 及び 環境省「廃棄物等の処理」に関するウェブサイト]
そして、廃棄物処理法では「排出事業者責任」が厳格に定められています。
これは、廃棄物を排出した事業者(太陽光パネルの所有者)が、その処理を他者に委託した場合でも、最終的に処分されるまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずる責任を負う、という考え方です。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条、第12条]
万が一、委託した業者が不法投棄を行った場合、排出事業者自身も措置命令や罰則の対象となる可能性があります。
【2022年7月開始「廃棄等費用積立制度」とは?】
こうした背景から、廃棄費用の確保を確実にするため、2022年7月に「廃棄等費用積立制度」が始まりました。
●対象:FIT/FIP制度の認定を受けた10kW以上のすべての太陽光発電事業者。
●内容:国が認定した外部機関(電力広域的運営推進機関)に対し、買取期間が終了する10年前から、発電事業者が廃棄費用を積み立てることを義務付ける制度。
●目的:将来の廃棄費用を確実に確保し、事業者の倒産などで行き場のないパネルが発生するリスクを低減し、適切な処分を促すこと。
3.【法人向けケーススタディ】工場の屋根の太陽光パネル(非FIT)、廃棄のポイントは?
近年、FIT制度を利用しない「自家消費型太陽光発電」を導入する法人が急増しています。この場合の廃棄ルールは、国の制度との関わりで特に注意が必要です。
【排出責任は100%「エンドユーザー」にある】
自家消費型太陽光であっても、法人の事業活動に伴って排出される太陽光パネルは、例外なく廃棄物処理法上の「産業廃棄物」です。したがって、エンドユーザーは法律に定められた排出責任を100%負うことになります。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3条、第12条]
【廃棄費用積立制度の「対象外」となる】
財務・経理の観点から極めて重要な点として、FIT/FIP認定を受けていない自家消費型太陽光パネルは、「廃棄等費用積立制度」の対象外となります。
つまり、太陽光発電を設置したエンドユーザーとなる会社は、将来発生するであろう撤去・処分費用を、すべて自社で計画的に準備しておかなければならないのです。将来の負債として認識し、長期修繕計画への組み込みや、会計上の引当金計上などの財務的対策が不可欠です。
4.気になる費用は?太陽光パネル廃棄のコスト徹底解剖
廃棄を考える上で、最も気になるのが費用でしょう。国の委員会での議論を基に、費用の考え方を解説します。
【費用の目安】
太陽光発電の買取価格などを決定する経済産業省の「調達価格等算定委員会」では、将来の廃棄費用についても議論されています。
その中で、事業用太陽光(主に地面に設置する野立て)の解体・撤去・処分費用の推計値として、「1kWあたり1.1万円~1.4万円」と試算・提示されており、これが1つの目安となっています。
ただし、この数値は主に野立ての平均的なケースを想定したものであり、工場の屋根など、高所での作業には以下の費用が大きく影響します。
●足場設置費用:安全な作業のために足場が必要な場合、規模に応じて数十万円以上の追加費用が発生します。
●作業難易度:屋根の形状や高さ、搬出経路の確保の難しさによって、追加の工事費や人件費がかかる場合があります。
上記費用は変動要因があるため、最終的な費用は必ず専門業者から見積もりを取得し検討することをお勧めします。
【相談から完了までの廃棄に関わるスケジュールと流れ】
廃棄のプロセスは、「廃棄物処理法」に則って進める必要があります。一般的な流れを解説します。
●業者選定・契約:廃棄物処理法に基づく許可を持つ専門業者を選定し、契約します。
●撤去工事:電気事業法に基づく保安規制を遵守し、感電などの危険がないよう安全に撤去工事を行います。
●収集運搬・処分:許可を持つ業者が、法令に準拠した方法で収集運搬・処分(リサイクルまたは埋立)を行います。
●マニフェストによる管理:排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、処理の各工程が完了したことを確認し、その写しを「5年間保存」する義務があります。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3]
全体としては、相談から完了までおよそ1ヶ月~2ヶ月程度を見ておくと良いでしょう。
5.【重要】廃棄のために必要な書類「マニフェスト」とは?
太陽光パネルを産業廃棄物として処理する上で、法律で定められた最も重要な書類が「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。
【マニフェストの役割】
マニフェスト制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、処理の流れを自ら把握し、不法投棄の防止や適正な処理を確保することを目的としています。
排出事業者は、委託した廃棄物が最終処分まで完了したことを、返送されてくるマニフェストの写しで確認する義務があります。
【法的義務としての保管】
排出事業者は、交付したマニフェストと、各工程の処理業者から返送されてくる写しを、それぞれ「5年間保存」しなければなりません。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の26、第8条の28等]
これは法令で定められた明確な義務であり、違反した場合は罰則の対象となります。
6.失敗しない!信頼できる廃棄業者の選び方
排出事業者責任を全うするためには、信頼できる業者を選ぶことが最も重要です。廃棄物処理法に基づき、確認すべきポイントを解説します。
【必要な「許可」を持っているか確認する】
業者を選定する際は、自治体から以下の許可を得ているか、許可証の提示を求めて必ず確認してください。
●産業廃棄物収集運搬業許可:廃棄物を収集し、処理施設まで運搬するために必要な許可。パネルを撤去する場所と、運搬先の処理施設がある場所の両方の都道府県(または政令市)の許可が必要。
●産業廃棄物処分業許可:廃棄物をリサイクル、または埋立処分するために必要な許可。
これらの許可証で、「事業の範囲」に「ガラスくず」「金属くず」などが含まれているか等を確認することが必要です。
[出典: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条、第14条の4]
いかがでしたでしょうか?
太陽光パネルを廃棄したい「その時」になって慌てないために、今から正しい知識を身につけ、太陽光パネルの状況を把握し、準備を進めることが大切です。
弊社でも、太陽光パネル廃棄に関するご相談を承っております。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。