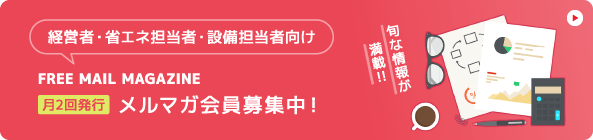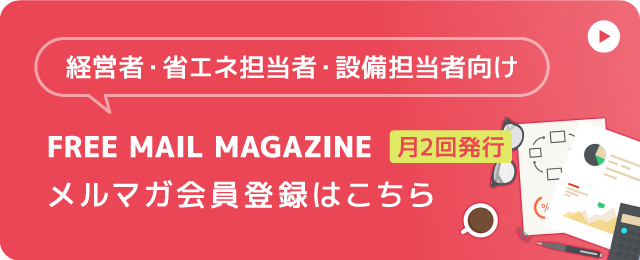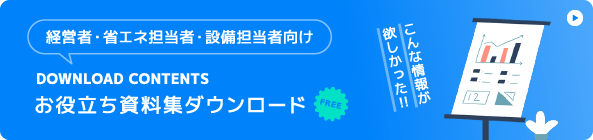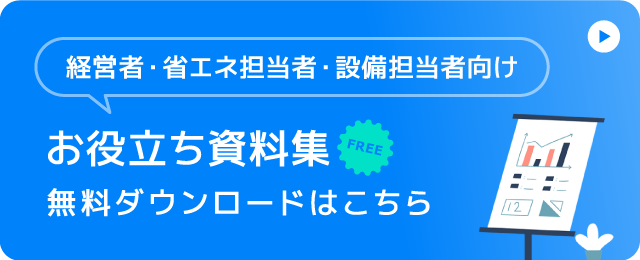コラム
コンテンツ
カーボンニュートラルやGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向け、企業の省エネ・脱炭素化投資の重要性がますます高まっています。一方で、エネルギーコストの高騰が続いており、省エネ関連の設備投資負担は依然として重い状況です。
そのような中、既に来年度(令和8年度)の国の予算編成の土台となる「概算要求」が各省庁から出揃っており、企業向けの省エネ・脱炭素関連補助金は「継続・拡充」される見通しとなっています。
今回は、令和8年度の省エネ関連補助金の解説とともに、活用できる設備やスケジュール感をお伝えさせていただきます。
1.令和8年度の省エネ補助金動向:概算要求から見える「3つのトレンド」
令和7年8月末に各省庁が提出した概算要求(来年度、この分野にこれだけ予算が欲しい、という要望書)を見ると、国のエネルギー政策のトレンドが読み取れます。省エネ関連補助金もこの潮流に沿って設計されています。
トレンド①・・・GX(グリーントランスフォーメーション)への本格シフト
いわゆる「古い設備を高効率なものに交換する」という単純な省エネ対策だけではなく、国が目指すのは、「電化」や「燃料転換」を通じてエネルギー構造を変革する「GX」です。
●補助金の傾向
従来の化石燃料(重油、灯油、都市ガス等)を使う設備から、ヒートポンプや高周波誘導炉(IH)といった「電気で動く設備への転換」、あるいは都市ガスから「水素混焼への転換」など、「エネルギーの使い方を根本から変える」投資への支援が、令和8年度は手厚くなっています。
トレンド②・・・「エネルギー効率(経産省)」と「CO2削減(環境省)」
省エネ関連補助金は、主に経済産業省と環境省の2つが管轄しています。各省の視点は似ているようで、以下のように重点が異なります。
●経済産業省の視点
主に「省エネルギー率(%)」や「エネルギーコスト削減(円)」を重視します。これらによる企業の競争力強化を目的としています。
●環境省の視点
主に「CO2排出削減量(t-CO2)」と「削減の費用対効果(円/t-CO2)」を重視します。これらによる地球温暖化対策及び貢献度合いを目的としています。
このように、自社の投資が「省エネ効果」か「CO2削減量」のどちらを強くアピールできるかで、狙うべき補助金が変わってくる、ということです。
トレンド③・・・EMSと「エネルギー需要の最適化」
設備を導入して終わり、ではなく、EMSやDR(デマンドレスポンス)のように、導入した設備を「いかに賢く使うか」が問われています。
●補助金の傾向
FEMS(工場向け)やBEMS(ビル向け)の導入と、それを管理・運用する「エネマネ事業者」との連携を必須とする補助金枠は継続されます。加えて、AIによる需要予測や、電力需給ひっ迫時に節電協力するDR対応機器の導入には加点が見込まれます。
2.令和8年度の主要補助金解説
※ご注意点
記載する情報は、令和8年度の「概算要求」および令和7年度の「実績」に基づく予想です。 補助金の正式名称、予算額、補助率、対象製品、公募要領は、令和8年1~3月頃に発表される「確定情報」を必ずご確認ください。
① 経済産業省系・・・「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」(仮称)
上記は、令和8年度の概算要求で約1,810億円の予算が要求されている、企業向け省エネ支援の代表的な補助金です。令和7年度同様に、以下の4類型を踏襲することが予想されています。
(A) 設備単位型(先進事業)
■概要
「とにかく早く、確実に省エネ設備を更新したい」企業向けの、認知度が高い補助金で、SII(環境共創イニシアチブ)などの執行団体に予め登録された高効率設備(=型番が決まっている製品・設備)を導入する事業です。
■特徴
申請が比較的シンプルで、採択スピードも速い傾向にあります。
補助率は1/3、補助上限は1億円程度(令和7年度実績)と予想されています。
■令和7年度の対象製品(一部)
【空調・給湯関連】
高効率空調:ダイキン工業『VRV』、三菱電機『シティマルチ』、日立『フレックスマルチ』など、トップランナー基準値(APF)を満たすビル用マルチエアコンや店舗・事務所用パッケージエアコン
産業ヒートポンプ:前川製作所、三菱重工サーマルシステムズなどが提供する、工場の蒸気や温水を作るための空気熱・水熱・排熱利用ヒートポンプ
業務用給湯器:リンナイ、ノーリツ、パロマ製の高効率ガス給湯器『エコジョーズ』の業務用モデルなど
【動力・熱源】
高性能ボイラー:三浦工業、日本サーモエナーなど、高いボイラー効率を誇る貫流ボイラーや水管ボイラー
高効率コージェネレーション:ヤンマー、三菱重工などのガスコージェネシステム
変圧器(トランス):日立、東芝、富士電機製のトップランナー基準対応アモルファス変圧器
【照明】
制御機能付きLED照明器具:パナソニック、アイリスオーヤマ、東芝ライテック等の、人感・調光センサーやスケジュール制御が可能な高効率LEDベースライトや高天井照明
【その他】
冷凍冷蔵設備:パナソニック、フクシマガリレイ、ホシザキ製のインバータ制御を搭載した業務用冷凍冷蔵庫、ショーケース
(B) 工場・事業場型(オーダーメイド事業)
■概要
「工場プロセス全体を抜本的に見直したい」企業向けの補助金です。上記(A)のような型番品ではなく、複数の機器を組み合わせて自社専用の省エネシステムを構築・導入する大規模投資に対するものとなっています。
■特徴
機械設計やエンジニアリングを伴います。高い省エネ率(事業所全体で10%以上等)の達成が求められますが、補助上限が最大15億円と大型補助金となっています。
(C) 電化・脱炭素燃転型(GX推進枠)
■概要
従来の化石燃料(重油、灯油、都市ガス)の使用を前提としたプロセスから、電気や低炭素燃料へ転換する事業に対する補助金です。
■特徴
GXへの貢献度が最も高く、補助上限も優遇される見込みです(例:電化は最大5億円)。
■令和7年度の対象となった投資例
【ボイラー・給湯の電化】
(転換前)A重油焚き蒸気ボイラー
(転換後)産業用ヒートポンプ給湯器システムを複数台導入し、高温水を製造
【工業炉の転換】
(転換前)鋳造工場のコークス溶解炉や、アルミ溶解用のガス反射炉
(転換後)高周波誘導炉に入れ替え、電気で金属を溶解する
(D) エネルギー需要最適化(エネマネ事業)
■概要
設備と運用の両方で省エネしたい企業向けの補助金です。
■特徴
EMS(エネルギー管理システム)の導入と、国に登録された「エネマネ事業者」との契約(エネルギー管理支援サービスの利用)がセットで必須となります。
■対象となる投資例
・FEMS(工場向け)/ BEMS(ビル向け)の導入。(例:パナソニック、三菱電機、アズビル等のEMSパッケージ)
・EMSと連動する空調・照明・生産設備の制御機器(インバーター、センサー類)の導入。
②環境省系・・・「工場・事業場における先導的な脱炭素化推進事業(SHIFT事業)」の後継事業
■概要
令和8年度も「地域脱炭素推進交付金」など、形を変えつつも補助金が継続されます。環境省は「CO2削減量(t-CO2)」や「CO2削減の費用対効果(円/t-CO2)」を重要視しており、設備導入だけではない付加価値を出す必要があります。
■特徴
令和7年度の実績では「電化・燃料転換を伴わない、単純な高効率化改修は補助対象外」となるケースがありました。
例えば、「高効率なガスボイラーに入れ替える」のは対象外になりやすく、「ガスボイラーからヒートポンプ(電化)に入れ替える」のは歓迎される、という傾向です。
■令和7年度対象となった投資例
【電化・再生可能エネルギー熱利用】
地中熱ヒートポンプ、バイオマスボイラー、太陽熱利用システムの導入
【未利用熱の活用】
工場排熱、下水熱、温泉熱などをヒートポンプで回収し、給湯や冷暖房に利用するシステム
【自然冷媒を使用した設備】
フロン系冷媒ではなく、CO2(R744)やアンモニア(R717)などの「自然冷媒」を使用した冷凍冷蔵設備への更新
3.経産省系と環境省系:どちらを選ぶべきか?
【経産省系が向くケース】
■「高効率なガスボイラー」「高効率なコンプレッサー」「LED照明」など、型番品をシンプルに入れ替えたい場合
■工場プロセス全体を見直し、省エネ率(%)を追求したい場合
■電化や燃料転換を伴わない、同一燃料間(例:ガス→ガス)の高効率化更新の場合
【環境省系が向くケース】
■電化・燃転型や自然冷媒など、国の脱炭素政策に直結する投資
■「A重油からヒートポンプへの転換」など、CO2削減のポテンシャルが大きい(=費用対効果が高い)場合
■経産省の補助金では省エネ率の要件を満たせないが、CO2削減量は大きい、という場合
4.採択率アップ!補助金申請を成功させる「具体的」ポイント
補助金は「早い者勝ち」ではなく「優秀な計画書」の順に採択されます。ぜひ、以下のポイントをご参考ください。
ポイント①・・・「ストーリー性」のある申請書を作成する
■NG例
「古いA設備を、新しいB設備に更新したい。補助金は●万円欲しい。」
■OK例
【課題】 「当社はA設備が老朽化し、同業他社比でエネルギーコストが●%高い。また、取引先(大手)から『CO2排出量削減』の要請が年々強まっている。」
【解決策】 「最新のB設備(経産省(A)設備単位型 対象製品)を導入する。これにより、エネルギー使用量が●%削減(省エネ率達成)できる。」
【波及効果】 「結果、年間●万円のコスト削減と、●●t-CO2の排出削減を見込む。浮いたコストで新規採用を行い、CO2削減をPRして大手取引先との関係を強化し、受注を拡大する。」
ポイント②・・・数値的根拠(省エネ率・削減量)を「ベンダー任せ」にしない
■NG例
カタログ上の「定格出力」だけで計算。「●kWの旧型」→「●kWの新型」に入れ替えるから、●kWの削減として申請する。
■OK例
実測データに基づき、「旧型は実負荷率●%(実質●kW)で常時稼働。新型はインバータ制御により、平均●kWの負荷に対し、実消費電力●kWで運転可能になる。したがって削減効果は●kWである」といった、運用実態に即した計算書を提出します。
5.令和8年度補助金に向けた準備とスケジュール
「公募が始まってから準備する」では、絶対に間に合いません。理想的なスケジュールは以下の通りです。
ステップ①:現状把握と「課題の特定」(令和7年12月末までに)
■エネルギー使用状況の「見える化」
どの設備が、いつ、どれだけエネルギーを使っているか(電力デマンド、ガス使用量など)を把握する。
■課題の特定
「どの設備が古いか」だけでなく、「自社の製造プロセスのどの部分が、最もエネルギーを使っているか」を特定する。
ステップ②・・・情報収集と「業者との連携開始」(令和8年1月~3月までに)
■GビズIDプライムの取得
現在の補助金申請は、「jGrants(Jグランツ)」という電子申請システムを使います。このログインに必要なアカウント取得には2~3週間必要です。
■製品選定の開始
ステップ①で特定した課題に基づき、複数の設備ベンダー等に相談し、補助金を見据えた製品提案を受けます。
ステップ③・・・申請準備(公募開始:令和8年3月下旬~4月頃)
■公募要領の確認
正式な公募要領の発表後、ベンダーの提案が、どの事業区分に合致するか、要件をすべて満たしているか、最終確認します。
■相見積の取得
補助金によっては申請に必須です(2社以上求められることが多い)。
ステップ④・・・申請・採択・事業開始(令和8年5月~)
■申請
jGrantsから電子申請を行います。締め切り直前はサーバーが混雑するため、余裕を持って提出します。
■審査・採択発表
■交付決定・事業開始
採択後、事務局との手続きを経て「交付決定通知」が届きます。
この通知が届く前に、設備の発注・契約・支払いを行うことは原則禁止です。これが発覚すると、採択が取り消されます。
いかがでしたでしょうか?
省エネ対策は多岐にわたる一方で、導入目的や効果次第で、補助金の選び方も変わってきます。
省エネ設備導入で補助金を活用する際には、余裕を持った準備が必要になります。春の公募開始と同時に、完成度の高い申請書でスタートダッシュができるよう、各種対応を進めていきましょう。
弊社でも省エネ設備に関するご相談を随時受け付けております。
お気軽にお問合せください。