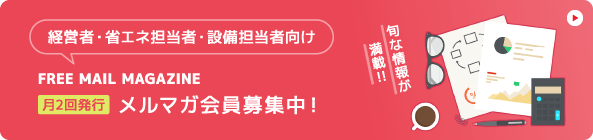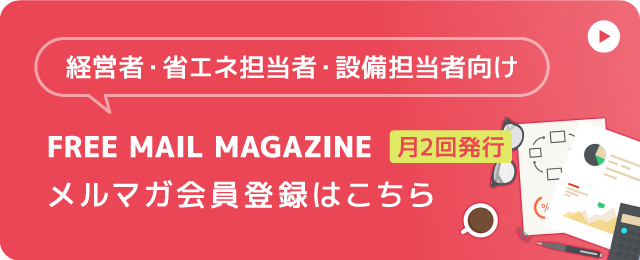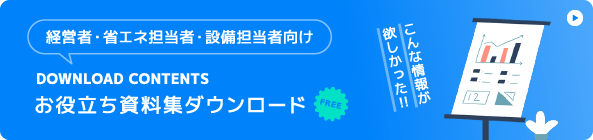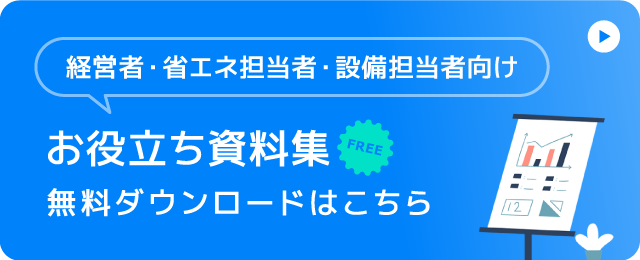コラム
コンテンツ
脱炭素社会の切り札として、今、大きな注目を集める「系統用蓄電池」。再エネの導入拡大に不可欠な系統用蓄電池は、電力システムの安定化に貢献するだけでなく、新たな投資対象としても熱い視線を浴びています。しかし、その実態やビジネスモデル、導入におけるハードルについては、まだ十分に知られていないのが現状です。
本コラムでは、系統用蓄電池ビジネスの概要を、初心者にも分かりやすく、かつ投資を検討する事業者が知りたい情報まで解説します。
1.そもそも系統用蓄電池とは?
系統用蓄電池とは、発電所や変電所のように、電力系統(電力ネットワーク)に直接接続される大規模な蓄電システムのことです。その基本的な役割は、電力の「需要」と「供給」のバランスを最適化することにあります。
電気が余る時(昼間の太陽光発電ピーク時など)・・・・・・・・蓄電池に「充電」
電気が足りない時(夕方の需要ピーク時や無風時など)・・・・・蓄電池から「放電」
このシンプルな仕組みにより、太陽光・風力などの変動する再エネ電源の出力を平準化し、電力系統全体の安定性を保ちます。製品は、リチウムイオン電池を巨大なコンテナに格納したものが主流です。テスラ(Tesla)やLGエナジーソリューションといった海外勢に加え、TMEICやGSユアサといった国内メーカーも高品質な製品を提供しており、プロジェクトの目的や予算に応じて様々な選択肢が存在します。
そして、このビジネスチャンスを逃すまいと、大手企業が続々と系統用蓄電池ビジネスへ参入をしています。
例①:関西電力とオリックス
和歌山県紀の川市で国内最大級の蓄電所(容量113MWh)を稼働させたほか、北海道でも大規模プロジェクト(合計351MWh)を発表。電力会社のノウハウと金融の知見を融合させています。
例②:ENEOSホールディングス
製油所跡地などを活用し、自社の再エネ発電所との連携や、電力市場での運用を戦略的に進めています。三菱総合研究所と共同で蓄電池の最適運用システムを開発するなど、技術力にも磨きをかけています。
例③:パシフィコ・エナジー
太陽光発電開発の雄が、その経験を活かして蓄電池事業に本格参入。北海道や福岡県で蓄電所を稼働させ、再エネと蓄電池を組み合わせた新たな価値創造を目指しています。
これらの動きは、系統用蓄電池がもはや実証実験の段階ではなく、収益を生み出す「事業」のフェーズに完全に移行したと言えるでしょう。
今後の市場については、経済産業省のデータを見ても、系統用蓄電池の導入に向けた事業者の意欲は非常に高く、電力会社への接続検討申込量は急増しています。
2024年の国内定置用蓄電池の導入量は2.5GWを超え、過去10年で飛躍的に伸びました。
しかし、世界の導入量から見れば日本のシェアはまだ数%。中国が約50%、米国が約30%を占める現状を考えれば、日本の市場は「これから」です。2050年のカーボンニュートラル達成という国家目標に向け、今後、国策として導入が強力に後押しされることは間違いなく、市場は爆発的な成長期を迎えることが予測されます。
2.系統用蓄電池のビジネスモデルとは
系統用蓄電池は、単なる社会貢献インフラではありません。高度な運用によって、確かな収益を生み出すポテンシャルを秘めた「投資アセット」です。その収益の源泉となる市場と、概算のシミュレーションについて解説します。
現在の系統用蓄電池ビジネスは、主に以下の3つの電力市場で収益を上げるハイブリッド型が主流です。
①卸電力市場(JEPX):
最も基本的なビジネスモデルで、「安い時に電気を買って(充電し)、高い時に売る(放電する)」ことで利ざやを得る「裁定取引(アービトラージ)」です。再エネの導入拡大により、昼間は電気が余って価格が暴落(時には0.01円/kWhに)し、夕方の需要期には高騰するなど、価格差が拡大傾向にあり、収益機会が増えています。
②需給調整市場:
電力の安定供給を担う「調整力」を取引する市場です。急な天候変化による発電量の変動や、発電所のトラブルなど、予測と実績のズレ(インバランス)を調整するために、電力広域的運営推進機関(OCCTO)が調整力を募集します。応答速度が速い蓄電池は、特に一次調整力や三次調整力①②といった、素早い対応が求められる商品で価値を発揮し、待機しているだけでも対価(容量単価)が得られるため、安定した収益基盤となります。
③容量市場:
将来(4年後)の電力供給力(kW)を確保するための市場です。発電設備や蓄電池などが「将来、これだけの供給能力を提供できます」と約束することで、その対価を受け取れます。長期的な収益の安定化に寄与します。
これらの市場の特性を理解し、AIなどを活用して最適なタイミングで充放電を繰り返す運用戦略が、収益を最大化する鍵となります。
また、肝心の「費用感」についてですが、設備費・工事費: 技術革新により価格は低下傾向にあります。
2025年時点では設備費と工事費を合わせて1kWhあたり7~8万円程度が一つの目安です。
特に、系統連系費用(工事費負担金)は最も変動が大きく、事業性を左右する最大の不確定要素です。
接続先の変電所までの距離が遠かったり、周辺の電力網の増強工事が必要になったりすると、数億円単位の負担金が発生するケースもあります。事前の入念な調査が不可欠です。
土地代についても、購入、または賃借で異なります。郊外の工業地帯などで、坪単価数万円〜という土地もあれば、都心近郊では高騰します。広さは2MW/8MWhクラスで最低でも300坪(約1,000㎡)程度は必要となります。
3.設置前に知るべき3つの注意点
有望な市場でありますが、誰でも簡単に成功できるわけではありません。系統用蓄電池ビジネスを成功に導くためには、専門的な知見に基づき、いくつかの重要なハードルを越える必要があります。
【Point 1】土地の条件
最適な土地を見つけることが、プロジェクトの成否を分ける第一歩です。
土地においては、以下の3つの点に注意すべきです。
①系統への近さ
最寄りの変電所に近く、高圧線や特別高圧線が付近を通っていることが絶対条件です。距離が遠いほど前述の系統連系費用が膨らみます。
②広さと形状
必要な面積を確保できるかはもちろん、コンテナの搬入やクレーン作業が可能な、整形地であることが望ましいです。
③法令・条例のクリア
都市計画法の用途地域、消防法(危険物施設としての規制)、自治体独自の条例など、法的な制約をクリアできる土地でなければなりません。ハザードマップを確認し、災害リスクが低いことも重要です。
【Point 2】系統の条件
良い土地が見つかっても、電力系統に「空き」がなければ電気を流すことはできません。
空き容量を確認するために、まずは管轄の電力会社(一般送配電事業者)のウェブサイトで公開されている「系統情報」を確認し、接続を希望するエリアの送電線に空き容量があるかを確認します。
そして、空き容量がある、もしくは対策工事で接続可能と判断した場合、電力会社に正式な「接続検討」を申し込みます。
ここで、技術的な接続可否や、必要な工事内容、そして前述の「工事費負担金」の見積もりが提示されます。この検討プロセスには、通常3ヶ月程度の期間を要します。
このプロセスは非常に専門的であり、電力システムに関する深い知見が求められるため、経験豊富な協力会社のサポートが不可欠です。
【Point 3】運用開始までの期間
投資を決定してから、実際に収益が生まれるまでには、想像以上に長い期間が必要です。
主な内容
① 開発・計画フェーズ
●事業計画策定、土地の確保、資金調達、接続検討
期間:6ヶ月~
② 許認可・契約フェーズ
●電力会社との接続契約、各種法令に基づく許認可取得、EPC(設計・調達・建設)業者選定・契約
期間:6ヶ月~
③ 建設フェーズ
●土地造成、基礎工事、機器搬入・据付、電気工事、系統連系工事
期間:6ヶ月~1年
④ 試運転・運転開始
●試運転、各種試験、商業運転開始
期間:1~2ヶ月
特に、特別高圧で連系する場合の系統連系工事は、電力会社の都合にも左右され、工事費負担金の入金後から18ヶ月〜20ヶ月程度かかることも珍しくありません。この長いリードタイムを織り込んだ、精緻な事業計画と資金計画が成功の鍵となります。
いかがでしたでしょうか?
系統用蓄電池は、脱炭素化の要請と電力システムの構造変化が生み出した、新領域のビジネスです。市場が本格的な成長期に突入していく今、的確な知識と戦略をもって参入すれば、大きな先行者利益を得ることも可能です。
弊社も系統用蓄電池事業のお手伝いをさせていただきます。ご興味をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。